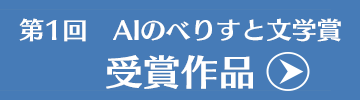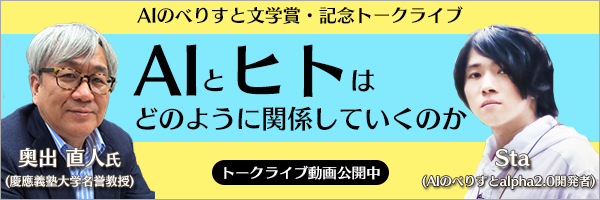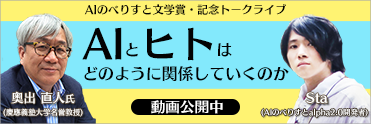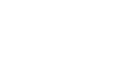


「AIのべりすと文学賞」は、「AIのべりすとβ2.0」を使って人とAIが共同する新しい創作活動を支援するために創設されました。2025年第2回を開催し、223作のご応募をいただきました。最優秀賞をはじめとする各賞を発表します。
「AIのべりすとβ2.0」は、日本語で史上最大、総2テラバイト以上のコーパスからフルスクラッチで訓練した小説AIです。



受賞作:「おじいちゃんは国家反逆者」
作 者:事の顛末
純文学、ライトノベルなどジャンルを問わず最も優れた作品に贈られます。
賞金 50万円・「AIのべりすと」プラチナ会員権12ヶ月分

受賞作:「語られぬ君 読まれぬ詩」
作 者:だん がらり
最も優れた純文学作品に贈られます。
賞金 10万円・「AIのべりすと」プラチナ会員権12ヶ月分

受賞作:「怪異系女子モロイさん」
作 者:晃月芽依也
最も優れたエンタメ/ライトノベル作品に贈られます。
賞金 10万円・「AIのべりすと」プラチナ会員権12ヶ月分

受賞作:創作落語「一人心中」
作 者:スートラ
最も優れたショート作品に贈られます。
賞金 10万円・「AIのべりすと」プラチナ会員権12ヶ月分
▼受賞作品の公開と今後について▼
受賞作品は、「AIのべりすと文学賞・作品集」として、書籍化を検討しています。
審査委員長(敬称略)

橘川 幸夫
(デジタルメディア研究所代表)
審査委員(敬称略)

柳瀬博一
[東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授(メディア論)]
慶應義塾大学経済学部を卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP)に入社し「日経ビジネス」記者を経て単行本の編集に従事する。『小倉昌男 経営学』『日本美術応援団』『社長失格』『アー・ユー・ハッピー?』『流行人類学クロニクル』『養老孟司のデジタル昆虫図鑑』などを担当。「日経ビジネスオンライン」立ち上げに参画、のちに同企画プロデューサー。TBSラジオ「柳瀬博一・Terminal(やなせひろいちターミナル)」のほかラジオNIKKEI、渋谷のラジオ「渋谷の柳瀬博一研究室」でパーソナリティとしても活動。 2018年3月に日経BPを退社し、同4月より東京工業大学教授に就任。2020年11月、編集者時代から20年以上あたためてきた論考をまとめた『国道16号線』を出版。NPO小網代野外活動調整会議理事。

池澤春菜
[声優]
声優、舞台女優、歌手、エッセイストとして活躍。第20代日本SF作家クラブ会長。小説家・詩人、翻訳家の池澤夏樹は父。小説家・詩人の福永武彦は祖父。キャリアカウンセラー、ギリシャ料理研究家の池澤ショーエンバウム直美は母。詩人の原條あき子は祖母。声優としての代表作に、『ザ・キング・オブ・ファイターズ』シリーズ(麻宮アテナ)、『とっとこハム太郎』(ロコちゃん)、『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』(星馬豪)、『ケロロ軍曹』(西澤桃華)、『マリア様がみてる』(島津由乃)、『ふたりはプリキュア』(ポルン)などがある。

KAHUA
[AIアート・ディレクター, アーティスト]
KAHUA VR LAB.主宰。神戸出身で芦屋在住のアーティストであり、生成AIやVR映像、ヴァーチャル空間での3Dお絵描きなど、最新技術を駆使したアート制作を専門としています。アーティスト育成とAI映画、MV制作、AIアイドルやAI音楽レーベル、キャラクター制作に注力。個人や企業向けにAIアート講座を提供し、デジタルトランスフォーメーションを支援。世代別の居場所づくりと教育にも注力。ビジョン「現代美術への挑戦を通じて、新たなアートシーンを切り開くことを目指します。創造力と技術力を融合し、新たな価値を創造し、世界に出ることを目指します」

ダ・ヴィンチ・恐山
[ライター]
作家・ライター。ダ・ヴィンチ・恐山名義でコンテンツ制作会社バーグハンバーグバーグのWebライティングや動画出演などを行う傍ら、品田遊名義では小説家として活動している。既刊書籍は短編集『止まりだしたら走らない』『名称未設定ファイル』のほか、哲学対話小説『ただしい人類滅亡計画』など。AIを活用したコンテンツ制作に興味があり、最近は「AIのべりすと」を利用して原稿を執筆することも多い。
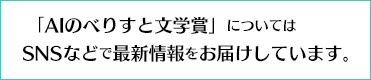
©2025 AI Novelist Literary Award. All Rights Reserved.